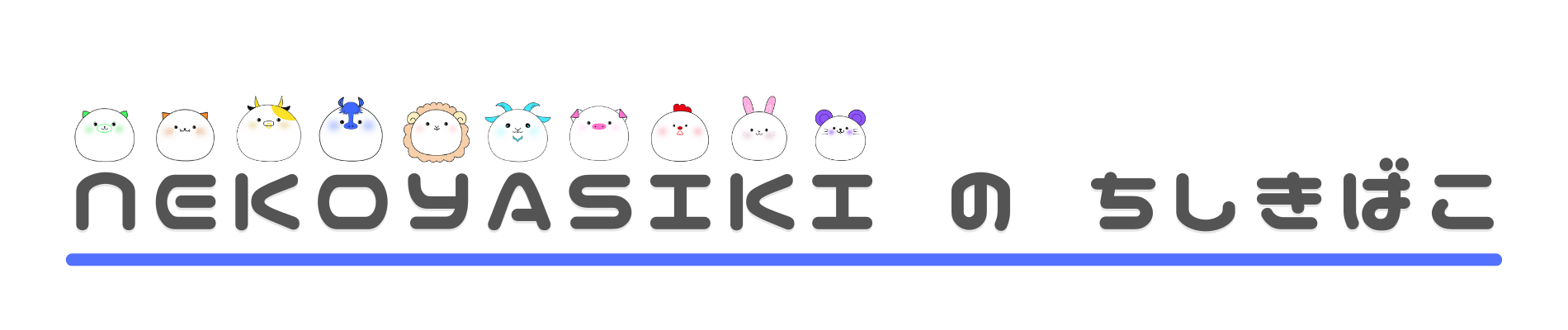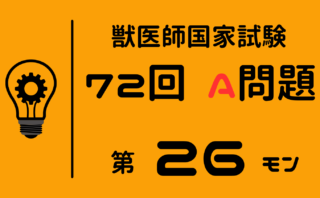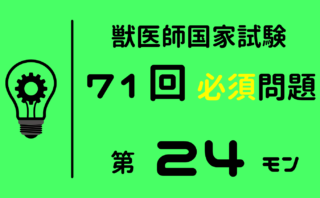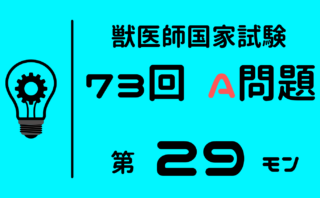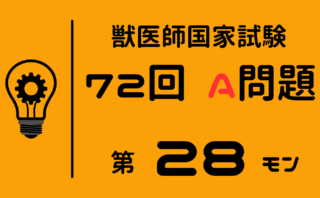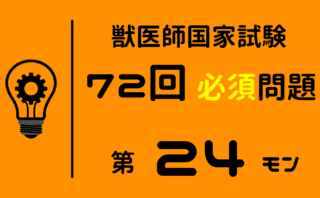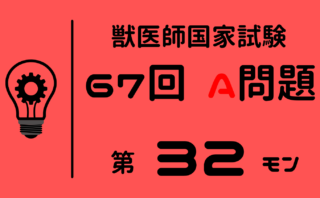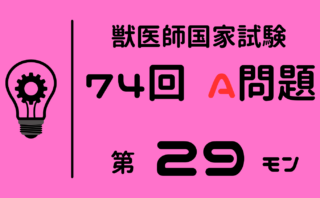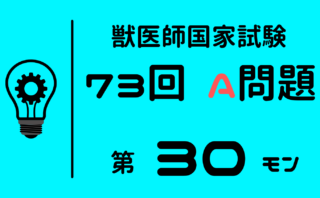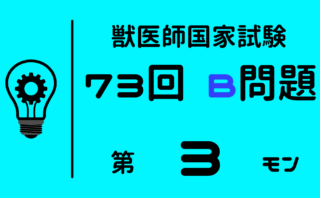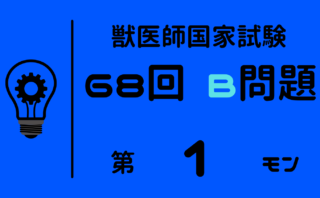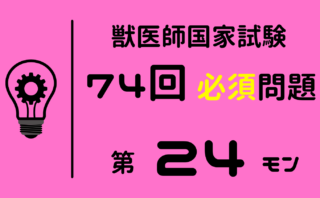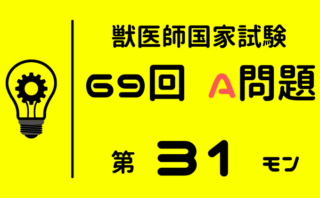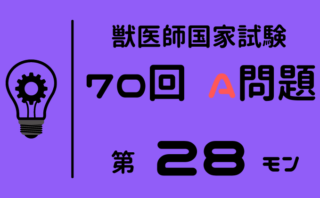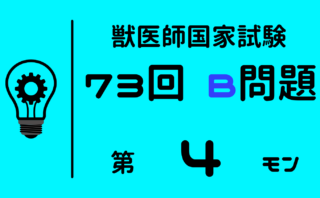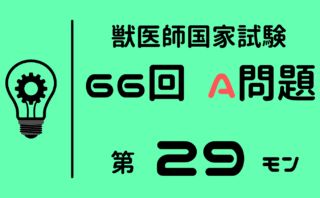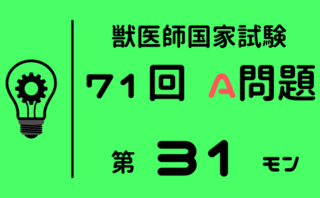総論
生体反応
① 第Ⅰ相反応(ミクロソーム内)
第Ⅰ相反応は、「酸化」「還元」「加水分解」です。この反応は基本的にミクロソームで行われます。代表例は「シトクロームP450(CYP)」です。CYPは薬物を”酸化反応”で代謝しています。
ミクロソーム分画ってなんだよ?
結論:細胞を破壊し、遠心分離したときにできる沈殿層のことです。「核分画」「ミトコンドリア分画」「ミクロソーム分画」「その他」の4つに大きく分けられます。
多くの酵素はこのミクロソームに分布しています。
② 第Ⅱ相反応
第Ⅱ相反応で、転移酵素が活躍し水溶性が一段と増します。この転移酵素は動物により種差があります。
ミクロソーム分画でグルクロン酸抱合を
ミクロソーム以外で、硫酸抱合・グリシン抱合・アセチル化を行います。
ミクロソーム
で簡単に覚えられます。
ゴロ・覚え方
流れるブタ、焦るイヌ、グレる黒ネコ
グルクロン酸転移酵素と、グルタチオン転移酵素で迷う方が多いと思うので、「黒ネコ」とおぼえてくださいね。
薬の代謝
① どんな薬が吸収されやすいのか?
基本的に薬物は受動拡散で細胞膜を通過し、作用します。もちろん脂溶性物質は細胞膜を通過し易いですまた、分子型の方が消化管より吸収されやすいことが分かっています。
分子型の方が吸収されやすい!
酸性領域では酸性の薬が、アルカリ性領域ではアルカリ性の薬が分子型になりやすいです。これは「Henderson-Hasselbalch の式」によって決まります。
酸性の薬は酸性領域で解離しにくい!
解離と電離って似ているね。何が違うんだよ?
結論:2つのものが離れる現象が「解離」。その離れたものが電荷を持っていれば「電離」となります。
② 分布
薬物の運搬役は「アルブミン」です。アルブミンと薬物が”可逆的に”結合し、全身に回ります。残念なことにアルブミンは間質に出られないため、薬物が作用するためにはアルブミンフリーになる必要があります。
ワルファリンとの併用が推奨されないのはなぜ?
結論:ワルファリンはアルブミンとの結合力が強いからです。
併用された薬剤は、アルブミンへの結合率が低下します。結合していない薬物は容易に間質→細胞内へ進み作用が強くなったり、予期せぬ副作用が生じる可能性があります。
③ 消失
薬物の排出経路は、「尿」や「便」がありますね。基本的に水溶性の薬剤は尿から、脂溶性の薬剤は「肝臓」で代謝されてウンコとなって排出されます。
どうして座薬は速攻性があるの?
結論:座薬が吸収される動脈は、門脈に入らず直接心臓にいくからです。
乳汁移行
乳汁は間質液よりもアルカリ性なので、塩基性薬物の方が乳汁へ移行しやすいです。
塩基性薬物が乳汁移行しやすい!
薬理作用
- 胃内では塩基性の薬は吸収されない。
- 脂溶性が高いほど腸管で速やかに吸収される。
- 解離型の比率が高いほど小腸で速やかに吸収される。
- 小腸に達した薬はおもに能動輸送系で吸収される。
- 消化管より吸収された薬は初回通過効果を受けない。
1( a , b )が正解です。
- 作動薬の ED50値は〔A〕が最も大きい。
- 作動薬の ED50値は〔C〕が最も大きい。
- 〔A〕、〔B〕は完全作動薬である。
- 〔C〕は完全作動薬である。
- 〔D〕の前処置は〔A〕、〔B〕、〔C〕の作用には影響しない。
3
体内動態
- 分布容積が1l/kgの薬物は細胞外液のみに分布する。
- 2.(血漿中濃度曲線下面積)/(薬物の投与量)は全身クリアランスである。
- 一部の利尿薬は有機酸輸送系により尿細管内へ分泌される。
- (血液)/(ガス)分配係数が小さい吸入麻酔薬は神経組織への移行が速い。
- 経口投与した薬物の血漿中濃度変化は分布相と消失相から成る。
3
- CYP による反応は加水分解反応である。
- 腸管の CYP 活性は、肝臓のそれに匹敵する。
- 基質特異性は高い。
- 活性には動物種差が認められる。
- エリスロマイシン前処置により活性化される。
4
- アミノ酸抱合は、カルボン酸の CoA 誘導体にアミノ基を抱合する。
- アセチル抱合でのアセチル基の供与体はアセチル CoA である。
- 硫酸抱合は、ミクロソームの抱合酵素により触媒される。
- グルクロン酸抱合物には腸肝循環を繰り返すものがある。
- 抱合反応に関与する酵素を転移酵素(トランスフェラーゼ)と呼ぶ。
3
- 酸化
- 還元
- 加水分解
- グルクロン酸抱合
- 硫酸抱合
5
- 酸性薬は血漿中のアルブミンと結合しやすい。
- 塩基性薬は血漿中の al 酸性糖タンパク質と結合しやすい。
- 血漿タンパク質と結合した薬は毛細血管でろ過されない。
- 薬と血漿タンパク質との結合は非可逆的である。
- 薬が血漿タンパク質に結合すると薬理効果は現れにくい。
4
- バルビツール酸誘導体 ― 肝臓における代謝酵素の誘導
- β−ラクタム系抗生物質 ― 細菌の β ラクタマーゼ産生能獲得
- βアドレナリン作動薬 ― β アドレナリン受容体の脱感作
- サルファ剤 ― 細菌の葉酸合成能獲得
- 抗悪性腫瘍薬 ― 腫瘍細胞の P 糖タンパク質発現減少
5
コンパートメントモデル
- 血中半減期は A の方が⻑い。
- 経口投与した時の全身クリアランスは B の方が大きい。
- 静脈内投与で求めた分布容積は A の方が小さい。
- 経口投与した時の生体内利用率は B の方が高い。
- 消失速度定数は A の方が小さい。
4
- この薬は 2 コンパートメントモデルに従う。
- 投与直後の急激な血中濃度の減少(I)は血液から組織への薬の移行を反映している。
- A+B は時間ゼロにおける血漿中濃度と等しい。
- 体内蓄積のない薬物の場合、血漿中濃度のゆるやかな減少(II)は薬の体外への排泄を反映してい
る。 - この薬は筋や脂肪などの特定の組織あるいは細胞内には分布しにくい。
5
- 静脈内投与した時の初期血漿中濃度を薬物の投与量で割ると算出できる。
- 薬物が血漿中濃度と等しい濃度で分布していると仮定したときの容積を表す。
- 特定の組織に高濃度で蓄積する薬物では 1l/kg 以上になることがある。
- 分布が血液だけに限られる薬物では 0.5l/kg 以上となる。
- 細胞外および細胞内に均一に分布する薬物では 0.05l/kg 以下となる。
3( b , c )が正解です。
- 1.0 L / kg
- 1.5 L / kg
- 3.0 L / kg
- 20 L / kg
- 30 L / kg
1
1( a , b )が正解です。
心臓に係る薬剤
全身に血液を送る
強心薬を使用する目的は「心臓を動かして、全身に血液を送る(心拍出量を増やす)」ことになります。
心臓が送り出す血液量を増やすためには、次の2つのパラメータがあります。
① 心臓に速く動いてもらう「スピード」
② 心臓に強い収縮をしてもらう「パワー」
それを踏まえた上で、以下の強心薬を覚えましょう!
心拍数も、心収縮力も”バク上げ⤴”すれば良いのか?
結論:よくないです。
心拍出量を増やして血液を巡らせるのが本来の目的ですが、心臓が過剰に動いてしまうと相当な酸素を消費することになります。急性期やOPE中はさておき、慢性心不全時にはできるだけ心臓に負荷をかけないことが重要です。腎臓の項でより詳しく記述しています。
抗不整脈薬 ー 不整脈に抗う
以下の表は絶対に覚えましょう!
| 抗不整脈薬の分類 | 作用部位 | 代表薬 | |
|---|---|---|---|
| 第Ⅰ群 | Ⅰa | Na+チャネル | キニジン・プロカイン |
| Ⅰb | リドカイン | ||
| Ⅰc | フレカイニド | ||
| 第Ⅱ群 | β受容体拮抗 | プロプラノロール | |
| 第Ⅲ群 | K+チャネル | アミオダロン | |
| 第Ⅳ群 | Ca2+チャネル | ベラパミル・ジルチアゼム | |
「ジルチアゼム」「ベラパミル」は、血管拡張薬として使用しないのかよ?
結論:アムロジピンは、血管選択性が高いのに対し、「ジルチアゼム」「ベラパミル」は心臓にも作用し陰性変力作用を引き起こします。
カルシウム拮抗をすることで、ペースメーカの異常興奮、リエントリー、異所性電気活動を抑制させられる点で「不整脈改善薬」として使用されます。ちなみに、第Ⅳ群の不整脈薬です。
心臓への負担を減らす
腎臓に働く薬物と大部分が重なります。詳しくは、腎臓の方で説明します!
- 利尿薬
- ACE阻害薬
- アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
- 血管拡張薬
強心薬
- ホスホジエステラーゼ阻害薬は細胞内 cAMP を低下させる。
- β アドレナリン作動薬は細胞内 cAMP を増加させる。
- アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬は心肥大を抑制する。
- NO ドナーは動脈を拡張するが静脈は拡張しない。
- 強心配糖体は心筋細胞の Na+−K+ATPase 活性を促進する。
3( b , c )が正解です。
不整脈薬
その他